 福井弁護士会では、2008年から春先に地元の高校に支援弁護士を派遣し、高校生模擬裁判選手権を行ってきました。 この大会は、裁判員制度の実施に伴い、事実の多面的な見方や、 手続的正義(適正手続)という法的価値を高校生に身につけていただくために、検察側、弁護側に分かれ模擬裁判を行い、審査員の協議により優勝、準優勝などを決定しています。
福井弁護士会では、2008年から春先に地元の高校に支援弁護士を派遣し、高校生模擬裁判選手権を行ってきました。 この大会は、裁判員制度の実施に伴い、事実の多面的な見方や、 手続的正義(適正手続)という法的価値を高校生に身につけていただくために、検察側、弁護側に分かれ模擬裁判を行い、審査員の協議により優勝、準優勝などを決定しています。
毎年、開会式、試合、
閉会式(講評・表彰式)を
完全収録したDVDを作成しています→
法教育の出張授業は、2000年頃から行っています。
「法教育」とは、細やかな法律知識やノウハウ(例えば悪徳商法被害にあわないための注意点)以前に、身の回りの紛争や社会の基本的な問題について「自分で考え、公正に判断出来る能力(=法的資質)」を養おうとする教育です。米国におけるLRE(Law
Related
Education 法関連教育と訳されることもある)をひとつの範としています。
TR>
2016年7月30日(土)
金沢地方裁判所
(205,201号法廷を使用)
参加校 4校
試合数 4試合
この日は、
石川、東京、大阪、愛媛の
4カ所で同時開催
日弁連のページ
<午前>
第一会場
藤島高校(検察)vs 勝山高校(弁護)
第ニ会場
金沢二水高校(検察)vs 金沢大学附属高校(弁護)
< 午後> 第一会場
金沢大学附属高校(検察)vs 藤島高校(弁護)
第ニ会場
勝山高校(検察)vs 金沢二水高校(弁護)
優勝:勝山高校 準優勝:藤島高校
2016年4月29日(金)
福井地方裁判所
(1,2号法廷を使用)
参加校 4校
(但し4月10日の予選会には6校出場)
試合数 4試合
人数 54+28=82人
※集合記念写真に映っている人数
高校生+支援弁護士、審査員
高校生模擬裁判選手権2016
 午前 第一会場 勝山高校(検察側) vs 敦賀気比(弁護側)
午前 第一会場 勝山高校(検察側) vs 敦賀気比(弁護側)
第二会場 藤島高校(検察側) vs 大野高校(弁護側)
午後 第一会場 大野高校(検察側) vs 勝山高校(弁護側)
第二会場 敦賀気比(検察側) vs 藤島高校(弁護側)
優勝:藤島高校 準優勝:勝山高校(7月30日の中部北陸大会@金沢に出場予定)
※ 本年は、4月10日に福井弁護士会事務所にて、高志高校、敦賀高校を加えた6校による予選会を実施。4月29日は、高志高校、敦賀高校の生徒が高校生審査員として、第一会場、第二会場に入り、発表者を採点し、各参加校の優秀者(検察側、弁護側各1名ずつ)を「個人賞」として表彰した。
2015年8月1日(土)
福井地方裁判所
(第1、2号法廷を使用)
参加校 4校
試合数 4試合
この日は、
東京、大阪、香川、福井の
4カ所で同時開催
日弁連のページ
| <午前> 第一会場 金沢大附属(検察側) vs 大野高校(弁護側) 第二回場 金沢二水(検察側) vs 勝山高校(弁護側) |
| <午後> 第一会場 金沢二水(検察側) vs 金沢大附属(弁護側) 第二回場 大野高校(検察側) vs 勝山高校(弁護側) |
両校優勝:金沢大附属高校 福井県立勝山高校
2015年4月29日(水)
福井地方裁判所
(1,2,7号法廷を使用)
参加校 6校
試合数 6試合
人数 66+33=99人
※集合記念写真に映っている人数
高校生+支援弁護士、審査員
 午前 第一会場 敦賀高校(検察側) vs 藤島高校(弁護側)
午前 第一会場 敦賀高校(検察側) vs 藤島高校(弁護側)
第二会場 勝山高校(検察側) vs 大野高校(弁護側)
第三会場 敦賀気比(検察側) vs 高志高校(弁護側)
午後 第一会場 高志高校(検察側) vs 勝山高校(弁護側)
第二会場 藤島高校(検察側) vs 敦賀気比(弁護側)
第三会場 大野高校(検察側) vs 敦賀高校(弁護側)
2014年4月29日(火)
福井地方裁判所
(1,2,7号法廷を使用)
参加校 6校
試合数 6試合
人数 57+27=84人
※集合記念写真に映っている人数
高校生+支援弁護士、審査員
午前 第一会場 藤島高校(検察側) vs 大野高校(弁護側)
第二回場 敦賀気比(検察側) vs 高志高校(弁護側)
第三回場 金津高校(検察側) vs 敦賀高校(弁護側)
午後 第一会場 敦賀高校(検察側) vs 敦賀気比(弁護側)
第二回場 大野高校(検察側) vs 金津高校(弁護側)
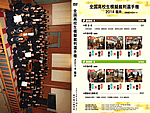 第三回場 高志高校(検察側) vs 藤島高校(弁護側)
第三回場 高志高校(検察側) vs 藤島高校(弁護側)
優勝:大野高校 準優勝:金津高校 三位:藤島高校
※敦賀気比高校は2回目、金津高校は3回目の出場
2013年4月29日(月)
福井地方裁判所
(1,2,7号法廷を使用)
参加校 6校
試合数 6試合
人数 56+34人
※集合記念写真に映っている人数
高校生+関係者
 高校生模擬裁判選手権2013 開催案内PDF
高校生模擬裁判選手権2013 開催案内PDF
午前 第一会場 金津高校(検察側) vs 高志高校(弁護側)
第二回場 敦賀高校(検察側) vs 藤島高校(弁護側)
第三回場 敦賀気比(検察側) vs 大野高校(弁護側)
午後 第一会場 藤島高校(検察側) vs 敦賀気比(弁護側)
第二回場 大野高校(検察側) vs 金津高校(弁護側)
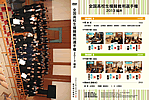 第三回場 高志高校(検察側) vs 敦賀高校(弁護側)
第三回場 高志高校(検察側) vs 敦賀高校(弁護側)
優勝:金津高校 準優勝:藤島高校 三位:大野高校
※敦賀気比高校は初出場
2012年4月30日(月)
福井地方裁判所
(1,2,7号法廷を使用)
参加校 6校
試合数 6試合
人数 54+27人
※集合記念写真に映っている人数
高校生+関係者
関西大会の結果:入賞なし
高校生模擬裁判選手権2012 開催案内PDF 参加6校に拡大
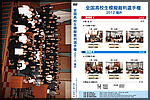 午前 第一会場 金津高校(検察側) vs 敦賀高校(弁護側)
午前 第一会場 金津高校(検察側) vs 敦賀高校(弁護側)
第二回場 藤島高校(検察側) vs 大野高校(弁護側)
第三回場 高志高校(検察側) vs 若狭高校(弁護側)
午後 第一会場 若狭高校(検察側) vs 藤島高校(弁護側)
第二回場 敦賀高校(検察側) vs 高志高校(弁護側)
第三回場 大野高校(検察側) vs 金津高校(弁護側)
優勝:藤島高校が関西大会の出場権を得ました。準優勝:金津高校 三位:大野高校 ※金津高校、若狭高校は初出場
2011年4月29日(金)
福井地方裁判所
(1号法廷、2号法廷)
参加校 4校
試合数 4試合
人数 45+25人
※集合記念写真に映っている人数
高校生+関係者
関西大会の結果: 入賞なし
高校生模擬裁判選手権2011 開催案内PDF 関西大会に2校出場
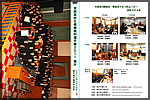 午前 1号法廷 敦賀高校(検察側) vs 高志高校(弁護側)
午前 1号法廷 敦賀高校(検察側) vs 高志高校(弁護側)
2号法廷 藤島高校(検察側) vs 大野高校(弁護側)
午後 1号法廷 高志高校(検察側) vs 藤島高校(弁護側)
2号法廷 大野高校(検察側) vs 敦賀高校(弁護側)
優勝:藤島高校、準優勝:高志高校が関西大会(2011.8.6)の出場権を得ました。 ※敦賀高校は初出場
2010年4月29日(木)
福井地方裁判所
(1号法廷、2号法廷)
参加校 4校
試合数 4試合
人数 45+22人
※集合記念写真に映っている人数
高校生+関係者
関西大会の結果: 入賞なし
高校生模擬裁判選手権2010 開催案内PDF この年から実際の法廷を使用
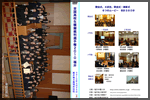 午前 1号法廷 藤島高校(検察側) vs 大野高校(弁護側)
午前 1号法廷 藤島高校(検察側) vs 大野高校(弁護側)
2号法廷 武生高校(検察側) vs 高志高校(弁護側)
午後 1号法廷 大野高校(検察側) vs 武生高校(弁護側)
2号法廷 高志高校(検察側) vs 藤島高校(弁護側)
藤島高校が関西大会の出場権を得ました。
2009年4月29日(水)
福井県教育センター
参加校 4校
試合数 4試合
人数 33+13人
※集合記念写真に映っている人数
高校生+関係者
関西大会の結果:準優勝
高校生模擬裁判選手権2009 4試合制に移行・採点方法も変更
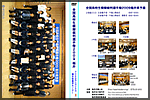 午前 A会場 高志高校(検察側) vs 藤島高校(弁護側)
午前 A会場 高志高校(検察側) vs 藤島高校(弁護側)
B会場 大野高校(弁護側) vs 武生高校(検察側)
午後 A会場 武生高校(検察側) vs 高志高校(弁護側)
B会場 藤島高校(弁護側) vs 大野高校(検察側)
藤島高校が関西大会の出場権を得ました。
2008年4月29日(火)
福井県教育センター
参加校 4校
試合数 3試合
人数 21+12人
※集合記念写真に映っている人数
高校生+関係者
関西大会の結果: 入賞なし
高校生模擬裁判選手権2008 募集要項 初開催
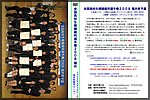 大阪大会の出場校枠の中に「福井県代表枠」を1校分確保した上で、県代表校決定のための福井県予選(武生高校、高志高校、大野高校、藤島高校の4チームが出場)を開催致しました。
大阪大会の出場校枠の中に「福井県代表枠」を1校分確保した上で、県代表校決定のための福井県予選(武生高校、高志高校、大野高校、藤島高校の4チームが出場)を開催致しました。
A会場 高志高校(検察側) vs 大野高校(弁護側)
B会場 武生高校(弁護側) vs 藤島高校(検察側)
決勝戦 武生高校(弁護側) vs 高志高校(検察側) 優勝:武生高校 大会の様子
2007年
日本弁護士連合会は、8月東京・大阪の両会場において、「高校生模擬裁判選手権2007」を開催。
第1回ということもあり、東京会場・大阪会場とも4校ずつの参加により開催され、東西決戦も行なわれませんでした。東京大会のDVDが福井弁護士会にも配布されました。
関連図書の紹介
はじめての法教育 みんなでくらすために必要なこと 全5冊 14,700円 日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」・編
「法律」の勉強ではなく、法的に考えるための「考え方」を身につける本。「法」の基本となるもっとも重要な5つの要素「自由・責任・ルール(権威)・公平・正義」についてとりあげ、読者が、エピソードをとおして自分自身の思考により、理解し、体得することを目的とした構成となっています。






